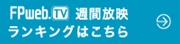近年、教育現場の環境整備事業の一環として、校庭を天然芝生舗装することが始まりました。また、都市部の学校では、地球温暖化によるヒートアイランド対策として効果があるという観点から、今後整備が加速されるものと思われます。
校庭を芝舗装するといっても、気候,目的,用途も異なり、建設コスト,維持管理も安いものではありません。また、校庭の使用頻度は、特定のスポーツ施設よりはるかに多く、ハードな使われ方をします。芝生文化の歴史が浅く、国土の狭いわが国では問題点が多くあります。この様なことから、一度は天然芝生舗装されても、維持管理等が大変だということから、人工芝,土舗装に変えられてしまうこともあります。
校庭を芝生舗装にするには、維持管理体制,気候,施工方法を十分に検討してから実施することが大切です。
本レポートは、この様な観点からまとめた資料です。
校庭芝生舗装の参考資料として御利用いただければと思います。

今日、世界で使われている芝生には多くの種類があり、日々改良されています。芝生を大雑把に分類すると、
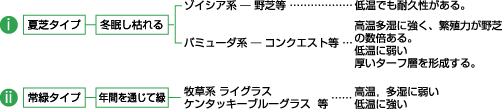
となります。芝生は生き物であり、環境によって生育状態が異なります。
芝の基本的性質は十分に認識しておくことが必要と思われます。
1. 芝生は、使われると磨り減ります。成長を回復させる時間が必要です
よって
● 床土の材質、芝生の種類を事前によく検討する。
● よく使われ、磨り減りやすい箇所の面積を事前に把握しておく。
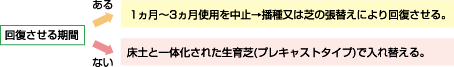
2. 芝生は成長します。刈込みが必要です。
活力のある状態にすればするほど、よく成長するため刈込み回数も多くなります。使用目的にあわせて十分な管理が必要です。
刈込み高さを低くしすぎると芝に多くのストレスを与え、病気等の発生原因になります。校庭では、30mm〜50mm高さが適していると思います。
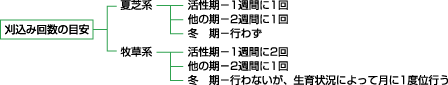
3. どんな芝生にとってもわが国では、通常4月〜6月、9月〜10月頃が一番生育に適した気候であり、よく生育する時期です。バミューダ系の芝では、体感温度が60℃近くのものもあり、6月〜9月頃に急成長する品種もあります。よって、芝生舗装の施工時期は、十分な検討が必要です。
4. 芝生が密生した状態で生育していれば、雑草は殆ど生えません。
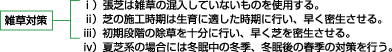
5. 夏芝系は11月頃〜3月中旬まで約5ヶ月間冬眠し、芝は枯れます。
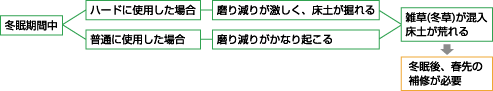
6. 常緑タイプは年間を通じて緑です。(積雪下においても緑色です)しかし、高温で湿気の多い夏場はストレスを多く受けます。夏場対策が必要となります。その対策としては、除菌剤の散布を行ないます。また、5℃以下になると芝はほとんど活性化しなくなります。
7. 夏場の潅水は夕方又は夜間か早朝に行い、日中には行わない。
その理由は
● 床土に浸透する量より蒸発する方が多い。
● 散水した水の温度が上昇し、かえって蒸れて芝にストレスを与えることになる。冬場は午前中に潅水した方が良い。

どのような施工方法で校庭の芝生舗装を実施しても、工事完了,検査直後は素晴らしい芝舗装ですが、使用開始後、下記の様ないろいろな問題点が発生します。



踏圧により床土の透水性が悪くなる


潅水不足による芝の生育不良












※ロ)、ホ)は施工方法で対処することが出来ますが、あとは維持管理で行うしかありません。
校庭の芝生舗装で一番重要なことは、きちっとした維持管理体制を作り、管理を続けることです。

建設費,維持管理費を大幅に下げる為には下記条件が必要です。
イ) 少量の雑草混入,裸地が出来る事を容認する。
ロ) 校庭の一部分、又は校舎等公共建築物の屋上にナーセリー(芝生生産場)を作る。
ハ) 地域住民により、有償で維持管理要員を組織し、維持管理を行う。
但し、機械等の設備は行政で負担する。また、初期段階は専門家による指導を受ける。(維持管理NPOを組織するのが最も良いと思います。)
ニ) 潅水等危険を伴わない作業は、生徒,職員等学校側で行う。(作業内容が十分理解出来るようになったら、生徒,学生アルバイトに提供するのも良い。)
ホ) ナーセリーの生育管理は専門家に委託し、簡単な作業(潅水等)は、生徒,職員等学校側で行う。(この点についても専門家の指導のもと、生徒,学生をアルバイトとして作業を行うと良い。)
ヘ) 休校期間中は校庭を使用しない事とし、計画的に維持管理を行う。その場合、使用する芝生の性質を良く理解し、気候と生育時期にあった作業内容のプログラムを専門家とともに作成する。
5−1)床土
校庭の現況土を改良して100%使用する。
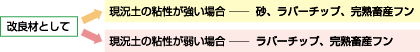
を使用します。この方法は米国等において、安い芝舗装の建設方法として行われています。ラバーチップの混入により硬度,透水性が大幅に改良され、完熟畜産フンの混合により保肥力が高まります。
5−2)芝生
芝生は夏芝系,牧草系どちらか選んで生育させたロール芝を張ることを基本とします。建設初期に3ヶ月養生期間が可能な場合には、播種又は、さし目工法にて施工をします。
ナーセリーで生産する芝生は、校庭で使用するものと同じにします。磨り減り等が起こった場合に、張替え用として生産した芝を使います。その回数は概ね1回〜2回,面積は校庭の20%〜30%と思われます。張替え時期等は、芝の種類,使用状況を見て専門家の意見を聞いて行います。
5−3)肥料
肥料はコーティングした180日対応のものを使用し、年1回程度追肥を行います。
5−4)目土
目土はラバーチップを使用します。これも米国,ヨーロッパで実績があり、米国では2,000t以上使用されています。ラバーチップの使用により芝生の根頭を保護し、生育を助けます。
5−5)エアレーション
エアレーションは基本的には行いません。
5−6)除菌剤の使用
夏芝系は、基本的には行いません。但し、状況によっては行う必要がある場合もあります。
牧草系は、必要がありますので使用します。
5−7)刈込み
刈込みは高刈を基本とします。40mm前後です。
5−8)潅水
潅水は手動による空中潅水方式です。
初期投資が掛かりますが、校庭下に雨水貯留を設置し、雨水を利用する事が望ましいと思います。
この様な方法で行えば、面積にもよりますが、建設費が1・当り2,000円〜4,500円、維持管理費が1平方メートル当り600円〜800円で可能と思われます。
但し、初期投資は各学校によって異なるため、含みません。

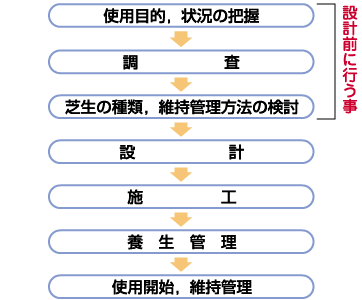
校庭は多目的に多くの人達に利用されます。
使用頻度も多く、整備されたスポーツ施設とは比較にならない程ハードに使用される。よって、設計,施工以前に維持管理方法を含めた十分な検討が特に必要と言えます。
1 使用目的,状況の把握
イ) 使用者の年齢,使用者数
ロ) スポーツの種類
ハ) 芝生化する面積
ニ) 特に使用頻度の多い箇所の面積
ホ) 年間使用日数,及び使用しない日数
ヘ) 部外者に開放するか,しないか?
ト) 1日に何人位が何時間使用するか?
2) 調査
イ) 芝生化を行う地域の気象状況
年間を通じての気温,降雨・降雪量,日照時間等を調べる。
特に、11月〜3月の最低気温,平均気温,氷点下の日数
6月〜9月の最高気温,平均気温,27℃以上の日数
は、芝の生育にとって重要な要件です。
ロ) 校庭の日当たり状況
ハ) 風通しの状態
3) 芝生の種類,維持管理等の検討
イ) 使用する芝生の種類,及び生育したロール芝を使うか?播種から始めるか?
ロ) 生育芝を近くから供給出来るかどうか?
ハ) 床土の材質
ニ) 潅水方法
ホ) 維持管理方法
上記3項目を検討した上で、芝生の種類,床土の材質,施工時期,施工方法,維持管理方法を決定し、その後

の手順で実施をします。
但し、
・)使用頻度が校庭全面で激しい場合
・)建物等で風通しが悪く夏場に湿気がかなり多い場所
・)適切な維持管理が不可能な場合
には、天然芝舗装は行うべきではありません。
こういった場合には、クッション層のあるロングターフ(30mm以上)を使った 人工芝舗装が適していると思います。また、クッション層に保水性舗装を行えれば、ヒートアイランド対策にも効果があります。
A)芝生の種類
使用する芝は下記の点を検討し、適切な品種を選定して下さい。芝は張芝を基本とします。播種にて行う場合には、長期間の養生が可能な場合にのみ行って下さい。
張芝には十分に生育した、雑草の混入していない、ロール状の芝を使用すること。
イ) 年間を通じて、高温,多湿の時期が短い地域(東北、北海道、標高の高い地区)では、牧草系が良い。
ロ) 年間を通じて、高温,多湿の時期が長い地域(関東以西)では、ゾイシア系、又はバミューダ系が良い。
・ 使用頻度がかなり多い場合には、繁殖力が強くターフ層を形成しやすいバミューダ系が良い。
・ 年間を通じて常緑を望む場合には、牧草系を使用し夏場の管理を十分に行う。
または、バミューダ系をベースとし、牧草系をオーバーシードする。
ハ) 日当りの悪い場所はゾイシア系,バミューダ系は生育が悪く不向きです。牧草系を使うと良い。
B)床土の材質
床土の材質としては、
イ) 経年変化しても団粒化しにくく,保水力が高く,透水性の良いもの。
ロ) 害虫の幼虫が繁殖しにくいもの。
ハ) 床土の硬度が経年変化しにくく、細粒化しにくいもの。
が適しています。
使用方法,建設コスト,維持管理コスト等を含めた観点から最終的に決定します。なるべく透水性が良く、富栄養化しない材質を選ぶべきでしょう。
C)潅水システム
潅水方法としては、
・ 床土にドリップチューブ等を埋設し、コンピューター制御により自動的に行う。
・ 手動,自動方式による空中潅水。
があります。維持管理システム,面積,コストから適した方法を選定すべきでしょう。また、空中潅水の場合には、なるべく水の粒子を小さくして散水する方が効率的です。
水は雨水を利用しましょう。雨水を地下貯留システムにより貯水し、利用します。このシステムならば、水道水,井戸水を使う場合と違い、社会生活に必要な飲料水等に、負荷を掛けずに済みます。容量の大きな地下貯留層を校庭下に構築すれば、防火水,トイレの水としても利用できます。
D)施工の時期
施工時期は、使用される芝生の種類が活性化する時期に合わせて行う事が最も重要です。
工期の関係から、芝生にとって最悪な時期(夏芝−11月〜3月、牧草系−7月〜8月)によく施工されていますが、なんらメリットはありません。(手間ひまが多くかかるだけです。)
計画段階から良く検討して行いましょう。
E)維持管理
建設方法については時間を掛けて十分検討されますが、維持管理については、十分な検討が行われず、生徒,父兄,先生に作業をさせるといった様な安易な考えがよくあります。芝生舗装は維持管理が最も重要です。
芝生文化の浅いわが国では、維持管理は専門の人達に委託すべきでしょう。
「そんな事をするとコストが掛かりすぎて、高くなってしまう」と言われますが、 マーケットで芝舗装が多くなれば、コストはかなり下がります。その為にも、県,市,区等広域な規模で校庭芝舗装を計画し、マーケットを育て、NPO活動により地域の専門家を育成しなければなりません。1校,1校が対応すべきではありません。このことは、生育させたロール芝の供給についても同じことが言えます。現に、芝生の先進国のコストは日本の半分以下です。
イ) 機械,人員
・ 1パーティー 3〜4名で、年間40,000平方メートル〜50,000平方メートルは管理可能です。
・ 芝刈機1台、芝ハギトリ機1台、軽四トラック1台、コントローラー1台
ロ) 芝の張替え
校庭の場合、磨り減り等により、全面積の20%〜30%を年間2回〜4回張り替えることを想定しておくことが必要です。
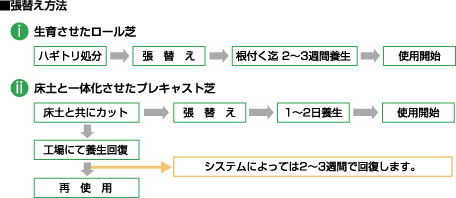
ハ) 刈込み
刈込みは適時に行い管理する。その時サッチ除去は十分に行う。
ニ) エアレーション
エアレーションはコストを安くするためにも、極力行わない床土システムを初めから採用する。
ホ) 追肥
追肥にはコーティング肥料を使用し、使用量を少なくします。
ヘ) 潅水
潅水作業は、設備さえあれば危険を伴うものでもありませんので、学校単位で生徒,職員に適時行わせる。
ト) 目土
目土には砂等は使用しないで、ラバーチップを使用する。砂等を使用した場合には養生期間が必要です。
チ) 除菌剤の散布
除菌剤の散布は数種類のものを変えて、病気発生の予防剤として少量散布する。散布剤は、人体に影響しないものを選んで行います。同一種の除菌剤を散布し続けると、菌が進化し除菌剤の効果が弱くなりますので注意が必要です。